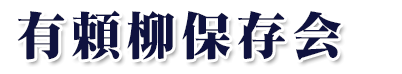立山開山に関するお話(小学生用)
立山開山に関するお話を3つのセクションに分けてご紹介しています。
下記のリンクから、興味のあるセクションをご覧ください。
📖 立山開山伝説
1300年前の大宝元年(701年)、佐伯有頼が白鷹を追って立山を開山したという伝説をお話しします。
- 狩りに出る有頼・・・立山開山伝説①
- 熊を追う有頼・・・立山開山伝説②
- 阿弥陀如来との出会い・・・立山開山伝説③
📚 立山開山に関するお話
1300年前に開山された開山伝説と立山信仰についての詳しいお話です。
- 1. はじめに
- 2. 佐伯有若
- 3. 佐伯有頼の誕生
- 4. 逃げた白い鷹
- 5. 白い鷹を捜して
- 6. 大熊を追って
- 7. 合掌念仏
- 8. 如来様
- 9. 玉殿の窟(岩屋)
💡 ご利用方法
各セクションは独立してお読みいただけます。また、各ページの下部にあるナビゲーションメニューを使って、他のセクションに移動することもできます。