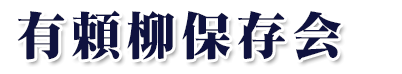立山開山
修験道の成立
廣瀬 誠 著
「万葉集に「皇神のうしはきいます山」「神ながら御名に帯ばせる山」と敬 讃され、立山はまさに神山であった。ひと口に「神のうしはく山」といっても、 人里近い山は、山上に祠を建て、あるいは巨岩を磐境(いわさか)として注連縄(しめなわ)を張り、人々はそこに登って祭祠を営み、花見、歌垣などをたのしんだ。しかし、富士・立山・白山など天高くそそりたつ神山に対しては、むしろ土足で踏み登ることを慎み、山麗に拝所を設けて遥かに伏し拝むのみであった。それが「神ながら」の山であった。
そのような高山峻岳に対して、汗みどろになって攀(よ)じ登り、苦難の末、山頂 にたどりつき、山神から特別な験力(けんりき)を授かってくるという山岳宗教が出現した。 日本古来の山岳崇拝に、真言系・天台系の山岳仏教が直なり、支那(中国)民 間宗教の道教も加わって、 1つに練りあげられたもので、後世これを修験道と いい、修験道の行者を山伏(やまぶし)と称した。
修験道の始祖といわれるのは、役小角(えのおづぬ)という伝説的人物(実在の人物であるが、伝説で濃くいろどられた超人的存在)で、ふつう役ノ行者(えんのぎょうじゃ)という。役は工と読むのが正しいが、南をミンナミというように、撥音が加わってエンと読 みならわされている。役ノ行者が葛城山の一言主神(ひとことぬしのかみ)を叱りつけて使役し呪縛したという伝説もあるから、行者は古来の山岳神聖不可踏の思想を梢極的に打 破したのであろう。
役小角流罪の事実は「続日本紀(しょくにほんぎ)」文武天皇3年(699)の条に記され、「日本霊異記(りょういき)」には大宝元年(701)役行者昇仙の伝説が記されている。修験道はこのころから日本の山岳宗教に大きく影群を与えはじめたのであろう。古来、立 山の文武天皇大宝元年と伝えて来たことは、このような史的背娯とまったく無関係ではなかったと思われる。
明治26年、大日岳山中で双龍の飾りをつけた美しい錫杖頭が発見された。 明治40年、剣岳頂上でも力強い錫杖頭が発見された。ともに平安初期の作で、 のち国の璽要文化財に指定された。錫杖は修験道が山野跛渉のさい持ち歩く宗 教的呪具である。これらの遺品は平安初期、修験僧たちが立山山中を歩きまわり、峰々谷々を踏破した足跡をまざまざと示すものだ。 のち国の重要文化財に指定された^錫杖は修験道が山野 i加のさい持ち歩く宗 教的呪具である。これらの道品は平安初期、修映俯たちが立山山中を歩きまわり、峰々谷々を路破した足跡をまざまさを示すものだ。
そのような高山峻岳に対して、汗みどろになって攀(よ)じ登り、苦難の末、山頂 にたどりつき、山神から特別な験力(けんりき)を授かってくるという山岳宗教が出現した。 日本古来の山岳崇拝に、真言系・天台系の山岳仏教が直なり、支那(中国)民 間宗教の道教も加わって、 1つに練りあげられたもので、後世これを修験道と いい、修験道の行者を山伏(やまぶし)と称した。
修験道の始祖といわれるのは、役小角(えのおづぬ)という伝説的人物(実在の人物であるが、伝説で濃くいろどられた超人的存在)で、ふつう役ノ行者(えんのぎょうじゃ)という。役は工と読むのが正しいが、南をミンナミというように、撥音が加わってエンと読 みならわされている。役ノ行者が葛城山の一言主神(ひとことぬしのかみ)を叱りつけて使役し呪縛したという伝説もあるから、行者は古来の山岳神聖不可踏の思想を梢極的に打 破したのであろう。
役小角流罪の事実は「続日本紀(しょくにほんぎ)」文武天皇3年(699)の条に記され、「日本霊異記(りょういき)」には大宝元年(701)役行者昇仙の伝説が記されている。修験道はこのころから日本の山岳宗教に大きく影群を与えはじめたのであろう。古来、立 山の文武天皇大宝元年と伝えて来たことは、このような史的背娯とまったく無関係ではなかったと思われる。
明治26年、大日岳山中で双龍の飾りをつけた美しい錫杖頭が発見された。 明治40年、剣岳頂上でも力強い錫杖頭が発見された。ともに平安初期の作で、 のち国の璽要文化財に指定された。錫杖は修験道が山野跛渉のさい持ち歩く宗 教的呪具である。これらの遺品は平安初期、修験僧たちが立山山中を歩きまわり、峰々谷々を踏破した足跡をまざまざと示すものだ。 のち国の重要文化財に指定された^錫杖は修験道が山野 i加のさい持ち歩く宗 教的呪具である。これらの道品は平安初期、修映俯たちが立山山中を歩きまわり、峰々谷々を路破した足跡をまざまさを示すものだ。
熊と白鷹 ― 立山開山の伝承
以下、立山開山の伝承を説話風に記す。
しまった! 少年は拳をにぎりしめたまま、 呆然と天空の一点をにらみつづ けた。白鷹は1つの点となって青空のかなたに遠ざかっていった。
われに返った少年は、まっしぐらに鷹のあとを追って走り出した。 髪は乱れ、 足には血がにじんだ。 日が暮れると、 草を枕として寝たが、 朝目を覚ますとま た、 少年は鷹の飛び去った方角めがけて小走りに歩きつづけた。
少年は名を有頼といい、 越中守、 佐伯有若の一人むすこであった。 有若の館 は片貝川と布施川の落ちあう地点、 老柳の茂るところにあったという。 有頼少 年は父秘蔵の白鷹をこっそり持ち出し、父のまねをして鷹狩りをしてみたのであった。
鷹は有頼の手を放れて獲物に襲いかかったが、どうしたはすみか、獲物の小鳥は身をひるがえして鷹の鋭い爪をのがれた。
すると鷹はそのまま天高く飛び去ってしまった。有頼はあわてた。父秘蔵の鷹を逃がして、どうしておめおめ家に帰られるものか、どんなことがあっても取りもどしてみせるぞと、死に物狂いで鷹のあとを追跡したのであった。
幾日か追跡していくと、森の中から、片手に剣をさげ、片手に数珠を持った老人が現れ、「お前が探している鷹はこの方角だ」と指差し教えてくれた。「あなたはどなたで?」と聞きかえすと、「わしは刀尾天神」と名のった。うやうやしくお礼の言葉を述べ、教えられた方角へ行くと、やがで常願寺川の岸にたどり着いた。川の崖っぷち、大きな松野こずえには白鷹がつばさを休めているではないか。有頼はおどりあがった喜んだ。
手に餌をのせて呼ぶと、鷹は羽ばたきして飛び立ち、有頼の拳に舞い降りた。 鷹の爪がうれしいほど痛い。 しめた! と思ったとき、1頭の荒々しい熊が飛び出し、有頼めがけて襲いかかってきた。その瞬間、鷹はどこかへ飛び立ってしまった。
怒り心頭に発した有頼は、弓に矢をつがえ、憎き熊めと射放った。矢はぴしっと熊の胸を射抜き、鮮血がほとばしった。熊は矢を立てたまま山奥へまっしぐらへ逃げ走った。 なびき伏した草の間に点々と落ちた血のあとをつけて、 有頼は坂を登り、 谷 を渡り、また坂を登り、 追いつづけた。 疲れはてて草叢に倒れたが、口もとに あたった草を何気なく噛み、 その汁を吸うと、たちまち気力を回復し、また熊 を追跡した。
いつのまにか有頼は広々とした高原に出た。 そこには、 夏だというのに雪が 残っていた。雪を踏み、 岩をよじ、 藪を分け、 汗みどろになって登ってゆくと、 岩穴に熊の逃げこむ姿が見えた。
よし、こんどこそ逃がすものか。剛気な有頼は弓に矢をつがえ直し、 岩穴に はいろうとした。
急に、有頼はまぶしさを感じ、次の瞬間、目の前がまっ暗になり、気が遠く なった。
夢かうつつか分からぬうちに、 有頼は光り輝く仏さまを見た。仏さまの胸に は矢が突っ立ち、 したたり落ちる血は蓮台まで赤く染めていた。 その矢はまご うかたなく、自分の射た矢であった。 さては、熊と思って射ったのは仏さまで あったか。有頼驚き、 起き直り、ひれ伏してお詫びを申し上げていると、 有頼の耳もとに不思議な声が聞こえた。
「私は衆生を救うため、 この立山に地獄も極楽も現して、 人々の来るのを待っ ている。しかし、世の人はまだこの尊い山を知らない。 そこで私は鷹に姿を変 え、熊に姿を変えて、有頼、そなたをここまで導いてきたのだ。 世のすべての 人が立山にお参りできるよう努力せよ。有頼、頼むぞ」と。
そして仏さまの姿は消え、取り残された有頼は、 自失して岩穴の入口に座り つづけていた。
あたりがほのかに明るくなった。 有頼が目を見開くと、天を突くような岩山 が夜目に黒々と立ちはだかっていた。
高い空に夜明けの星が1つきらめいている。 やがて、 山ぎわがしだいに明る く、いよいよ明るく、 突如、 まっ赤な日輪が山の頂きにさし昇った。 有頼は思 わず合掌した。 日輪を背に、逆光にけぶってそそり立つ山の姿こそ、 まさしく 昨夜、夢うつつのうちに拝んだ仏さまの姿そのままではないか。有頼は仏さま のお声を思い出した。
「夢ではない。たしかに聞いた! 今もはっきり耳もとに残っている!」 涙がはらはら頬を伝った。
有頼は感激のあまり、 弓を切り捨てた。 矢も折り捨てた。 「自分は仏門に入り、 僧となって、この霊山立山を開くために一生をささげよう」とかたく決心した。 弓も矢も、着衣も、 びっしょり夜霧にぬれていた。
山を下った有頼は、 麓に薬勢上人という徳の高い僧がいると聞き、 薬勢の庵 をたずね、事情を話して、 入門を願い出た。 薬勢の太い眉がぴくりと動いた。 薬勢はうなづきうなづき有頼の話を聞き、 その弟子入りを許した。 薬勢は有頼の頭を剃って、 慈興という僧名を与えた。
慈興は薬勢の教えを受けて仏道の修行に励み、やがて師弟協力して立山を開 くため全力を尽くした。 草を刈り、 藪を切り払い、 けわしい坂に道を作り、 谷 川には籠の渡りを取りつけた。予想以上に困難な仕事の連続であったが、 慈興 はひたすらに仏の教えを念じて、 この難事業を成し遂げた。
麓の大河、 常願寺川の南側には、 薬勢上人が本宮寺 光明山・ 報恩寺などの 寺を建てた。 大河の北側には、 慈興上人が芦峅寺根本中堂・禅光寺・岩峅寺な どの寺を建て、これらの寺々を立山登拝のための根拠地とし、 また僧たちの修 行の場とした。
立山を神と祀る神社が古くから山麗各地に点在していたが、これらの古い神 社は、新しく建てた寺と結ばれ、 社寺一体の姿で運営され、立山大権現とあがめられた。
芦峅寺の根本中宮に対して、 岩峅寺の神社は麓ノ大宮と呼ばれ、 相並んで 立山信仰の基地とされた。 大河の南側の本宮寺のかたわらには立蔵権現が祀ら れていた。 中宮 大宮 本宮の名称、アシクラ・イワクラ・タチクラの地名は いずれも重要な意味を持っていた。 有頼が白鷹を追跡したとき、 これを助けた 土地の神々、 刀尾天神や森尻権現も、手厚く祀られた。
慈興上人、俗名有頼が初めて仏さまに出あい、 仏さまのお告げを聞いた山上 の岩穴は、 玉殿 岩屋と名づけられ、 特別な聖地とされた。 岩屋には幾体もの 石仏が安置されたが、 また山に登って修行するときの宿泊所の役にも立てられた。
この岩屋に座り、はるか下の谷あいから、 淙々とひびいてくる浄土川の音を 聞くとき、 慈興は、仏に出あったおりの感激を思い返し、 初心に立ちかえるの であった。
有頼が鷹・熊を追跡して、 山を踏み分け、 霊山を開いたという特別のいわれ によって、 熊と鷹は立山の神獣神鳥として大切にされた。 熊と鷹の図柄は立 山のお護り札に使用された。 また神社の神紋には 「鷹の違い羽」 の紋が選ばれ、 社頭の幔幕にはこの鷹の羽のデザインがすがすがしく染め抜かれた。
薬勢・慈興上人は協力して、人々に立山信仰を説きひろめた。
このこうごうしい山に登れば、おのずから心が清められて、 生きながら仏の 世界に近づくということを、 慈興は自分の貴重な体験を踏まえ、確信をこめて 説いた。けわしい山道を汗水たらして登ってゆくうちに、心も体も鍛えられて、 不思議な神の力が身に備わってくることも力説した。
悪いことをしてはならぬ、いたずらに生き物を殺して無益な殺生をしてはな らぬということを、 立山地獄谷のものすごい光景を示して説き、人々の道徳心・ 宗教心を高めるため、 心魂を砕いて説教した。
こうして、霊山立山の存在は日本中に知れ渡り、全国から多くの人々が登拝 するようになったのであった。
立山を開く大事業を成し遂げた慈興上人は、 83歳のとき、 みずからの命終 わる時がきたことを悟り、 芦峅寺の龍象洞の地下に入って定を組み、 しずかに 念仏を唱えた。 7日間、地下から念仏の声が聞こえたという。
以上が、 地もと芦峅 岩峅に語り伝えられて来た「立山開山縁起」 の大筋で あるが、 立山開山の縁起を記したもっとも古い文献は、鎌倉時代初頭にできた 『伊呂波字類抄』 の十巻本である。
それによると、 立山を開いたのは越中守佐伯宿禰有若自身であったという。 有若が鷹狩りをしていて、逃げた鷹のあとを追って、夏も雪のある高山に登り、 ここで出会った熊を射殺した。 ところが、その熊は金色の阿弥陀如来であった。 その場所から仰ぎ見ると、 そびえ立つ岩石の山の姿は仏のお姿さながらであった。 有若は感銘、 肝に銘じ、 菩提心 (仏道に入る心) を起こし、 弓を切り、髪 を剃り、名を慈興と改め、 薬勢上人を師として、師弟協力して立山を開き、大 河の南と北とに手分けして寺々を建立したという。
話の骨組みはほぼ同じであるが、 この伝承では、 仏のお告げを聞いたのでは なくて、射殺した熊が仏であったという奇瑞 (不思議でめでたい出来事)に驚 いて菩提心を起こしたとなっている。 熊が逃げこんだ玉殿岩屋のことも記されず、全般に話は簡素である。 何よりも、 開山の主人公が有頼少年ではなくて、 その父親の、 しかも越中守という、 いかめしい肩書きを持った佐伯有若となっ ている点が大きな違いだ。
有若は歴史上実在の人物で、 その署名した延喜5年(905) の古文書が、京 都の随心院という寺に現存している。 山を開いた僧の名は、 どちらの伝承も慈 興上人となっているが、 その俗名は有若、 すなわち越中国守とする伝えと、そ の子有頼少年とする伝えとがあるわけだ。 さらに、鎌倉時代末ごろの 『類聚 既験抄』という書物によると、 立山の麓の狩人が山で熊を射殺したが、 その熊は阿弥陀如来であった、 よって立山は開かれたといった程度の、きわめて簡単 な話だ。 細部を省力したためであろうが、 重大なのは、この伝承では、 立山を 開いた主人公は国守でもなく、 国守のむすこでもなく、 まったく無名の狩人と なっている点だ。 この素朴な形の話が、 立山開山伝説としてたぶんもっとも古 いものなのであろう。
山麗の名もなき狩人が、 立山山中で熊を殺し、 不思議な出来事に遭遇し、発 心して僧となり、 霊山立山を開いたというのが開山伝説の原形なのであろう。 その狩人はたぶん芦峅村落の佐伯一族だったのであろう。 おりしも名門の出、 佐伯宿禰有若が越中守として存在中で、 狩人が奇瑞に感じて出家し、 立山を開 くということを聞き、 これに深く賛同して、 経済的・行政的に多大の援助を与 えたのであろう。 狩人が自分と同じ佐伯姓であることからも、特別の親近感を 持ち、立山信仰を積極的に保護支援したのであろう。 『今昔物語』には、立山 信仰を大々的に援助して、 多くの人に奨めて写経をさせた国守の説話が記され ている。そのように国守有若も立山開山を手助けしたのであろう。 国守が身を のり出して立山開山を助けたことから、やがて国守自身が立山を開いたという ように語り伝えられたのではなかろうか。
次に、国守有若の話から少年有頼の話に変わってくるのはどうしてであろう。
越中では、古来、 男子には16歳になると必ず立山に登るしきたりであった。 民俗学の言葉でいうと、 通過儀礼ということになるが、 立山登拝をすませて初 めて一人前の男と社会的に認められ、 村の若衆組(青年団)に参加する資格を 与えられた。 結婚の資格も与えられた。立山登拝こそは越中男子一生に一度の 大事であった。 このような社会習慣が反映して、 国守有若の話から、そのむすこ16歳の少年有頼を主人公とする話に変わっていったのではなかろうかと思う。
その有頼という名は、江戸時代初期の延宝のころ (1675前後)有若の名に ちなんで創作されたもの、したがって有頼は架空の人物かともいわれているが、 もしかしたら、 古く、 実際に立山を開いた山麓の狩人の名が有頼で、 その名が 地もとに細々と伝承されていたのではなかろうか。その名を、国守有若のむす こという形で活用したのではないかと思う。二転三転した立山開山伝説も、 それぞれ根拠があったと思われる。 合理主義で割り切って、 一を正、 他を誤と して否定するような軽率な態度は慎まねばならぬと思う。
いずれにしても、 熊を殺したことによって仏を感得したという点が重要だ。 ささやかな命から、 宇宙の大生命を感じ取り、 その大いなる命のみなぎる聖地 に目ざめたのだ。 日本固有の神祇信仰では、すべてのものを神と認めた。 仏教もまたいっさいに仏性ありと説く。 そのような東洋的アニミズムが立山信仰の 根底に力強く息づいているのである。
立山開山伝説では、 鷹や熊が重要な役を務めるが、 立山の熊の話とよく似て いるのが紀州 (現和歌山県) 熊野の縁起だ。 熊野から吉野にかけての深山は修 験道の本場で、古くから多勢の人が交通の不便苦労もいとわず、いわゆる熊野 詣でをした霊地だ。その熊野の縁起では、 猟師近兼が熊を射ち、 そのあとを追 跡してゆくと、岩穴の中で熊は仏さまに変わっていた。 近兼は驚き、弓を切り、 頭を剃って僧になったという。 立山開山縁起と瓜二つの話だ。 熊野信仰の勢力 は絶大で、 熊野修験道は全国に及んでいたから、 立山もその影響を深く受けた のであろう。
熊は日本に棲息する最大の動物で、 古来、 特別に扱われて来た。 広く九州か ら中部にかけて、 猟師の間では、熊を狩猟すると、 まず熊の遺骸を拭き清め、 これを上座にすえ、 あるいは熊の月の輪に注連縄を張り、 供え物を飾り、 近隣・ 知人・親類の人々が集まり、 祝詞をあげたりしてから祝宴に移ったという。ま た熊を捕ると、 熊荒れといって、 山の天候が激変すると恐れられてきた。 泉鏡 花も作品の中で、 熊荒れを取り上げている。 このような熊に関する特別な感情 が、熊野縁起にも立山縁起にも噴き出ているのであろう。 熊を神獣とする信仰 習慣は、北辺のアイヌ、 さらにヨーロッパ北部からシベリアを越え、 北米の北 部にまで分布しているという。立山信仰も国際的視野から再検討しなければならないであろう。 『伊呂波字類抄』では立山を開いたのは越中国守佐伯有若である。『類聚既験 抄』では無名の狩人である。 おそらく無名の狩人というのがもとの姿であろう。 『今昔物語』には立山信仰を保護した越中国国司の話が出ている。 そのような 国司の存在した事実を背景にして、 国守開山伝承が成立したのであろう。 後世 にいたるまでの立山信仰護持村落、 岩峅 芦峅の実情から推して、立山を開い た無名の狩人が佐伯氏の一員であったことは確実であろう。
『和漢三才図会』および地もとの伝承では、 片貝川・布施川の落合点から白 鷹を追跡して常願寺谷にいたり、 熊を射て、 ついに立山を開いたと説く。 これ をもって佐伯一族が片貝・布施地方から常願寺谷へ移住した事実の反映と見る 故木倉豊信氏の見解がある。 これに対して、 佐伯氏はもともと常願寺谷の住民 であって、 片貝川云々は後世の造作であるとみる故石原与作氏の見解がある。
霊山開山伝説には、高僧が開いたという型と無名の狩人等が開いたという型 とがある。 白山の泰澄や男体山の勝道は高僧開山の例である。 熊野縁起は狩人 が熊を射たがその熊は仏であったという。 淡路先山では狩人忠太が猪を射たが その猪は仏であった、 狩人は山を開き寂忍上人となったと説く。 大山では猟師 依道が金色の狼を洞穴に追いつめたところ地蔵菩薩が現じ、狼は変じて登欖の 尼となった。 猟師は修行して金蓮上人となったと説く。 登欖尼は白山の融の姿、 立山の正字呂尼とほぼ同名である点も注目をひく。 同じ立山でも山崎村(現朝 日町)では猟師弥次右衛門が熊を追い、立山頂上まで追い上げたら熊は立山権 現に変じたと伝えている。 羽黒山縁起では、能除上人が聖徳太子の示現によっ て霊地におもむいたとき、猟師が手負の熊を追って通りかかったといって狩人伝 承の原型をちらつかせている。
このように話が多少くずれたり他系の伝説と複合したりしているが、 共通し た要素があることは誰の目にも明らかであろう。 狩人が獣を追い、射殺してみ たら仏であった。 狩人は感動して仏門に入り山を開くという形である。殺生を 業とする狩人が大物を射止めた瞬間、動物のいのちそのまま宇宙のいのちの尊 厳を感得するのである。 西欧ヒューマニズムのように人類独善でなく、生きと し生けるものに仏性を認める東洋的宗教感である。 仏教思想と融合した神道で あり、日本的アニミズムである。真の意味での「自然保護」の原点である。
このように山岳信仰研究上 「狩人」の伝承はきわめて重要である。 立山では 眼目立山寺創建のときにも、 立山権現が狩人の姿で現れ、 開寺を助けたと伝 えている。
立山開山伝承では熊の他に白鷹が重要な役割を果たしている。 白鷹にみちび かれた例としては婦負郡八幡村 (現富山市) 八幡宮の開基伝説がある。 羽黒山 でも能除上人は八尺の霊鳥にみちびかれたという。
熊と霊鳥がともに登場する最古の例は神武天皇大和入り伝承である。 鎮座す べき霊地を求めて各地を転々とする伝承はこれまた多く、 その典型は伊勢神宮 の伝承であるが、 婦負郡八幡宮の場合も立山の場合も、 また神武伝承もその1 つに数えてよいであろう。 立山開山伝承を研究するには、遠く記紀神話に遡り、 広く他地の伝承を集めて比較対照する必要を痛感するのである。
鷹は有頼の手を放れて獲物に襲いかかったが、どうしたはすみか、獲物の小鳥は身をひるがえして鷹の鋭い爪をのがれた。
すると鷹はそのまま天高く飛び去ってしまった。有頼はあわてた。父秘蔵の鷹を逃がして、どうしておめおめ家に帰られるものか、どんなことがあっても取りもどしてみせるぞと、死に物狂いで鷹のあとを追跡したのであった。
幾日か追跡していくと、森の中から、片手に剣をさげ、片手に数珠を持った老人が現れ、「お前が探している鷹はこの方角だ」と指差し教えてくれた。「あなたはどなたで?」と聞きかえすと、「わしは刀尾天神」と名のった。うやうやしくお礼の言葉を述べ、教えられた方角へ行くと、やがで常願寺川の岸にたどり着いた。川の崖っぷち、大きな松野こずえには白鷹がつばさを休めているではないか。有頼はおどりあがった喜んだ。
手に餌をのせて呼ぶと、鷹は羽ばたきして飛び立ち、有頼の拳に舞い降りた。 鷹の爪がうれしいほど痛い。 しめた! と思ったとき、1頭の荒々しい熊が飛び出し、有頼めがけて襲いかかってきた。その瞬間、鷹はどこかへ飛び立ってしまった。
怒り心頭に発した有頼は、弓に矢をつがえ、憎き熊めと射放った。矢はぴしっと熊の胸を射抜き、鮮血がほとばしった。熊は矢を立てたまま山奥へまっしぐらへ逃げ走った。 なびき伏した草の間に点々と落ちた血のあとをつけて、 有頼は坂を登り、 谷 を渡り、また坂を登り、 追いつづけた。 疲れはてて草叢に倒れたが、口もとに あたった草を何気なく噛み、 その汁を吸うと、たちまち気力を回復し、また熊 を追跡した。
いつのまにか有頼は広々とした高原に出た。 そこには、 夏だというのに雪が 残っていた。雪を踏み、 岩をよじ、 藪を分け、 汗みどろになって登ってゆくと、 岩穴に熊の逃げこむ姿が見えた。
よし、こんどこそ逃がすものか。剛気な有頼は弓に矢をつがえ直し、 岩穴に はいろうとした。
急に、有頼はまぶしさを感じ、次の瞬間、目の前がまっ暗になり、気が遠く なった。
夢かうつつか分からぬうちに、 有頼は光り輝く仏さまを見た。仏さまの胸に は矢が突っ立ち、 したたり落ちる血は蓮台まで赤く染めていた。 その矢はまご うかたなく、自分の射た矢であった。 さては、熊と思って射ったのは仏さまで あったか。有頼驚き、 起き直り、ひれ伏してお詫びを申し上げていると、 有頼の耳もとに不思議な声が聞こえた。
「私は衆生を救うため、 この立山に地獄も極楽も現して、 人々の来るのを待っ ている。しかし、世の人はまだこの尊い山を知らない。 そこで私は鷹に姿を変 え、熊に姿を変えて、有頼、そなたをここまで導いてきたのだ。 世のすべての 人が立山にお参りできるよう努力せよ。有頼、頼むぞ」と。
そして仏さまの姿は消え、取り残された有頼は、 自失して岩穴の入口に座り つづけていた。
あたりがほのかに明るくなった。 有頼が目を見開くと、天を突くような岩山 が夜目に黒々と立ちはだかっていた。
高い空に夜明けの星が1つきらめいている。 やがて、 山ぎわがしだいに明る く、いよいよ明るく、 突如、 まっ赤な日輪が山の頂きにさし昇った。 有頼は思 わず合掌した。 日輪を背に、逆光にけぶってそそり立つ山の姿こそ、 まさしく 昨夜、夢うつつのうちに拝んだ仏さまの姿そのままではないか。有頼は仏さま のお声を思い出した。
「夢ではない。たしかに聞いた! 今もはっきり耳もとに残っている!」 涙がはらはら頬を伝った。
有頼は感激のあまり、 弓を切り捨てた。 矢も折り捨てた。 「自分は仏門に入り、 僧となって、この霊山立山を開くために一生をささげよう」とかたく決心した。 弓も矢も、着衣も、 びっしょり夜霧にぬれていた。
山を下った有頼は、 麓に薬勢上人という徳の高い僧がいると聞き、 薬勢の庵 をたずね、事情を話して、 入門を願い出た。 薬勢の太い眉がぴくりと動いた。 薬勢はうなづきうなづき有頼の話を聞き、 その弟子入りを許した。 薬勢は有頼の頭を剃って、 慈興という僧名を与えた。
慈興は薬勢の教えを受けて仏道の修行に励み、やがて師弟協力して立山を開 くため全力を尽くした。 草を刈り、 藪を切り払い、 けわしい坂に道を作り、 谷 川には籠の渡りを取りつけた。予想以上に困難な仕事の連続であったが、 慈興 はひたすらに仏の教えを念じて、 この難事業を成し遂げた。
麓の大河、 常願寺川の南側には、 薬勢上人が本宮寺 光明山・ 報恩寺などの 寺を建てた。 大河の北側には、 慈興上人が芦峅寺根本中堂・禅光寺・岩峅寺な どの寺を建て、これらの寺々を立山登拝のための根拠地とし、 また僧たちの修 行の場とした。
立山を神と祀る神社が古くから山麗各地に点在していたが、これらの古い神 社は、新しく建てた寺と結ばれ、 社寺一体の姿で運営され、立山大権現とあがめられた。
芦峅寺の根本中宮に対して、 岩峅寺の神社は麓ノ大宮と呼ばれ、 相並んで 立山信仰の基地とされた。 大河の南側の本宮寺のかたわらには立蔵権現が祀ら れていた。 中宮 大宮 本宮の名称、アシクラ・イワクラ・タチクラの地名は いずれも重要な意味を持っていた。 有頼が白鷹を追跡したとき、 これを助けた 土地の神々、 刀尾天神や森尻権現も、手厚く祀られた。
慈興上人、俗名有頼が初めて仏さまに出あい、 仏さまのお告げを聞いた山上 の岩穴は、 玉殿 岩屋と名づけられ、 特別な聖地とされた。 岩屋には幾体もの 石仏が安置されたが、 また山に登って修行するときの宿泊所の役にも立てられた。
この岩屋に座り、はるか下の谷あいから、 淙々とひびいてくる浄土川の音を 聞くとき、 慈興は、仏に出あったおりの感激を思い返し、 初心に立ちかえるの であった。
有頼が鷹・熊を追跡して、 山を踏み分け、 霊山を開いたという特別のいわれ によって、 熊と鷹は立山の神獣神鳥として大切にされた。 熊と鷹の図柄は立 山のお護り札に使用された。 また神社の神紋には 「鷹の違い羽」 の紋が選ばれ、 社頭の幔幕にはこの鷹の羽のデザインがすがすがしく染め抜かれた。
薬勢・慈興上人は協力して、人々に立山信仰を説きひろめた。
このこうごうしい山に登れば、おのずから心が清められて、 生きながら仏の 世界に近づくということを、 慈興は自分の貴重な体験を踏まえ、確信をこめて 説いた。けわしい山道を汗水たらして登ってゆくうちに、心も体も鍛えられて、 不思議な神の力が身に備わってくることも力説した。
悪いことをしてはならぬ、いたずらに生き物を殺して無益な殺生をしてはな らぬということを、 立山地獄谷のものすごい光景を示して説き、人々の道徳心・ 宗教心を高めるため、 心魂を砕いて説教した。
こうして、霊山立山の存在は日本中に知れ渡り、全国から多くの人々が登拝 するようになったのであった。
立山を開く大事業を成し遂げた慈興上人は、 83歳のとき、 みずからの命終 わる時がきたことを悟り、 芦峅寺の龍象洞の地下に入って定を組み、 しずかに 念仏を唱えた。 7日間、地下から念仏の声が聞こえたという。
以上が、 地もと芦峅 岩峅に語り伝えられて来た「立山開山縁起」 の大筋で あるが、 立山開山の縁起を記したもっとも古い文献は、鎌倉時代初頭にできた 『伊呂波字類抄』 の十巻本である。
それによると、 立山を開いたのは越中守佐伯宿禰有若自身であったという。 有若が鷹狩りをしていて、逃げた鷹のあとを追って、夏も雪のある高山に登り、 ここで出会った熊を射殺した。 ところが、その熊は金色の阿弥陀如来であった。 その場所から仰ぎ見ると、 そびえ立つ岩石の山の姿は仏のお姿さながらであった。 有若は感銘、 肝に銘じ、 菩提心 (仏道に入る心) を起こし、 弓を切り、髪 を剃り、名を慈興と改め、 薬勢上人を師として、師弟協力して立山を開き、大 河の南と北とに手分けして寺々を建立したという。
話の骨組みはほぼ同じであるが、 この伝承では、 仏のお告げを聞いたのでは なくて、射殺した熊が仏であったという奇瑞 (不思議でめでたい出来事)に驚 いて菩提心を起こしたとなっている。 熊が逃げこんだ玉殿岩屋のことも記されず、全般に話は簡素である。 何よりも、 開山の主人公が有頼少年ではなくて、 その父親の、 しかも越中守という、 いかめしい肩書きを持った佐伯有若となっ ている点が大きな違いだ。
有若は歴史上実在の人物で、 その署名した延喜5年(905) の古文書が、京 都の随心院という寺に現存している。 山を開いた僧の名は、 どちらの伝承も慈 興上人となっているが、 その俗名は有若、 すなわち越中国守とする伝えと、そ の子有頼少年とする伝えとがあるわけだ。 さらに、鎌倉時代末ごろの 『類聚 既験抄』という書物によると、 立山の麓の狩人が山で熊を射殺したが、 その熊は阿弥陀如来であった、 よって立山は開かれたといった程度の、きわめて簡単 な話だ。 細部を省力したためであろうが、 重大なのは、この伝承では、 立山を 開いた主人公は国守でもなく、 国守のむすこでもなく、 まったく無名の狩人と なっている点だ。 この素朴な形の話が、 立山開山伝説としてたぶんもっとも古 いものなのであろう。
山麗の名もなき狩人が、 立山山中で熊を殺し、 不思議な出来事に遭遇し、発 心して僧となり、 霊山立山を開いたというのが開山伝説の原形なのであろう。 その狩人はたぶん芦峅村落の佐伯一族だったのであろう。 おりしも名門の出、 佐伯宿禰有若が越中守として存在中で、 狩人が奇瑞に感じて出家し、 立山を開 くということを聞き、 これに深く賛同して、 経済的・行政的に多大の援助を与 えたのであろう。 狩人が自分と同じ佐伯姓であることからも、特別の親近感を 持ち、立山信仰を積極的に保護支援したのであろう。 『今昔物語』には、立山 信仰を大々的に援助して、 多くの人に奨めて写経をさせた国守の説話が記され ている。そのように国守有若も立山開山を手助けしたのであろう。 国守が身を のり出して立山開山を助けたことから、やがて国守自身が立山を開いたという ように語り伝えられたのではなかろうか。
次に、国守有若の話から少年有頼の話に変わってくるのはどうしてであろう。
越中では、古来、 男子には16歳になると必ず立山に登るしきたりであった。 民俗学の言葉でいうと、 通過儀礼ということになるが、 立山登拝をすませて初 めて一人前の男と社会的に認められ、 村の若衆組(青年団)に参加する資格を 与えられた。 結婚の資格も与えられた。立山登拝こそは越中男子一生に一度の 大事であった。 このような社会習慣が反映して、 国守有若の話から、そのむすこ16歳の少年有頼を主人公とする話に変わっていったのではなかろうかと思う。
その有頼という名は、江戸時代初期の延宝のころ (1675前後)有若の名に ちなんで創作されたもの、したがって有頼は架空の人物かともいわれているが、 もしかしたら、 古く、 実際に立山を開いた山麓の狩人の名が有頼で、 その名が 地もとに細々と伝承されていたのではなかろうか。その名を、国守有若のむす こという形で活用したのではないかと思う。二転三転した立山開山伝説も、 それぞれ根拠があったと思われる。 合理主義で割り切って、 一を正、 他を誤と して否定するような軽率な態度は慎まねばならぬと思う。
いずれにしても、 熊を殺したことによって仏を感得したという点が重要だ。 ささやかな命から、 宇宙の大生命を感じ取り、 その大いなる命のみなぎる聖地 に目ざめたのだ。 日本固有の神祇信仰では、すべてのものを神と認めた。 仏教もまたいっさいに仏性ありと説く。 そのような東洋的アニミズムが立山信仰の 根底に力強く息づいているのである。
立山開山伝説では、 鷹や熊が重要な役を務めるが、 立山の熊の話とよく似て いるのが紀州 (現和歌山県) 熊野の縁起だ。 熊野から吉野にかけての深山は修 験道の本場で、古くから多勢の人が交通の不便苦労もいとわず、いわゆる熊野 詣でをした霊地だ。その熊野の縁起では、 猟師近兼が熊を射ち、 そのあとを追 跡してゆくと、岩穴の中で熊は仏さまに変わっていた。 近兼は驚き、弓を切り、 頭を剃って僧になったという。 立山開山縁起と瓜二つの話だ。 熊野信仰の勢力 は絶大で、 熊野修験道は全国に及んでいたから、 立山もその影響を深く受けた のであろう。
熊は日本に棲息する最大の動物で、 古来、 特別に扱われて来た。 広く九州か ら中部にかけて、 猟師の間では、熊を狩猟すると、 まず熊の遺骸を拭き清め、 これを上座にすえ、 あるいは熊の月の輪に注連縄を張り、 供え物を飾り、 近隣・ 知人・親類の人々が集まり、 祝詞をあげたりしてから祝宴に移ったという。ま た熊を捕ると、 熊荒れといって、 山の天候が激変すると恐れられてきた。 泉鏡 花も作品の中で、 熊荒れを取り上げている。 このような熊に関する特別な感情 が、熊野縁起にも立山縁起にも噴き出ているのであろう。 熊を神獣とする信仰 習慣は、北辺のアイヌ、 さらにヨーロッパ北部からシベリアを越え、 北米の北 部にまで分布しているという。立山信仰も国際的視野から再検討しなければならないであろう。 『伊呂波字類抄』では立山を開いたのは越中国守佐伯有若である。『類聚既験 抄』では無名の狩人である。 おそらく無名の狩人というのがもとの姿であろう。 『今昔物語』には立山信仰を保護した越中国国司の話が出ている。 そのような 国司の存在した事実を背景にして、 国守開山伝承が成立したのであろう。 後世 にいたるまでの立山信仰護持村落、 岩峅 芦峅の実情から推して、立山を開い た無名の狩人が佐伯氏の一員であったことは確実であろう。
『和漢三才図会』および地もとの伝承では、 片貝川・布施川の落合点から白 鷹を追跡して常願寺谷にいたり、 熊を射て、 ついに立山を開いたと説く。 これ をもって佐伯一族が片貝・布施地方から常願寺谷へ移住した事実の反映と見る 故木倉豊信氏の見解がある。 これに対して、 佐伯氏はもともと常願寺谷の住民 であって、 片貝川云々は後世の造作であるとみる故石原与作氏の見解がある。
霊山開山伝説には、高僧が開いたという型と無名の狩人等が開いたという型 とがある。 白山の泰澄や男体山の勝道は高僧開山の例である。 熊野縁起は狩人 が熊を射たがその熊は仏であったという。 淡路先山では狩人忠太が猪を射たが その猪は仏であった、 狩人は山を開き寂忍上人となったと説く。 大山では猟師 依道が金色の狼を洞穴に追いつめたところ地蔵菩薩が現じ、狼は変じて登欖の 尼となった。 猟師は修行して金蓮上人となったと説く。 登欖尼は白山の融の姿、 立山の正字呂尼とほぼ同名である点も注目をひく。 同じ立山でも山崎村(現朝 日町)では猟師弥次右衛門が熊を追い、立山頂上まで追い上げたら熊は立山権 現に変じたと伝えている。 羽黒山縁起では、能除上人が聖徳太子の示現によっ て霊地におもむいたとき、猟師が手負の熊を追って通りかかったといって狩人伝 承の原型をちらつかせている。
このように話が多少くずれたり他系の伝説と複合したりしているが、 共通し た要素があることは誰の目にも明らかであろう。 狩人が獣を追い、射殺してみ たら仏であった。 狩人は感動して仏門に入り山を開くという形である。殺生を 業とする狩人が大物を射止めた瞬間、動物のいのちそのまま宇宙のいのちの尊 厳を感得するのである。 西欧ヒューマニズムのように人類独善でなく、生きと し生けるものに仏性を認める東洋的宗教感である。 仏教思想と融合した神道で あり、日本的アニミズムである。真の意味での「自然保護」の原点である。
このように山岳信仰研究上 「狩人」の伝承はきわめて重要である。 立山では 眼目立山寺創建のときにも、 立山権現が狩人の姿で現れ、 開寺を助けたと伝 えている。
立山開山伝承では熊の他に白鷹が重要な役割を果たしている。 白鷹にみちび かれた例としては婦負郡八幡村 (現富山市) 八幡宮の開基伝説がある。 羽黒山 でも能除上人は八尺の霊鳥にみちびかれたという。
熊と霊鳥がともに登場する最古の例は神武天皇大和入り伝承である。 鎮座す べき霊地を求めて各地を転々とする伝承はこれまた多く、 その典型は伊勢神宮 の伝承であるが、 婦負郡八幡宮の場合も立山の場合も、 また神武伝承もその1 つに数えてよいであろう。 立山開山伝承を研究するには、遠く記紀神話に遡り、 広く他地の伝承を集めて比較対照する必要を痛感するのである。
有若・慈興と康済
以下、立山開山の伝承を説話風に記す。
しまった! 少年は拳をにぎりしめたまま、呆然と天空の一点をにらみつづけた。白鷹は1つの点となって青空のかなたに遠ざかっていった。
われに返った少年は、まっしぐらに鷹のあとを追って走り出した。髪は乱れ、足には血がにじんだ。日が暮れると、草を枕として寝たが、朝目を覚ますとまた、少年は鷹の飛び去った方角めがけて小走りに歩きつづけた。
少年は名を有頼といい、越中村、佐伯有若の一人むすこであった。有若の館は、片貝川と布瀬川の落ち合う地点、老柳の茂るところにあったという。有頼少年は父秘蔵の白鷹をこっそり持ち出し、父の真似をして鷹狩をしてみたのであった。
しまった! 少年は拳をにぎりしめたまま、呆然と天空の一点をにらみつづけた。白鷹は1つの点となって青空のかなたに遠ざかっていった。
われに返った少年は、まっしぐらに鷹のあとを追って走り出した。髪は乱れ、足には血がにじんだ。日が暮れると、草を枕として寝たが、朝目を覚ますとまた、少年は鷹の飛び去った方角めがけて小走りに歩きつづけた。
少年は名を有頼といい、越中村、佐伯有若の一人むすこであった。有若の館は、片貝川と布瀬川の落ち合う地点、老柳の茂るところにあったという。有頼少年は父秘蔵の白鷹をこっそり持ち出し、父の真似をして鷹狩をしてみたのであった。
立山開山
立山開山伝説に登場する人物、 越中守佐伯宿禰有若の名は、 国史に記載され ていなかったため、 史学界では、久しく架空人物あつかいされて来た。最初に 架空人物説を主張したのは加賀藩の大学者富田景周で、景周はその名著『越登 賀三州志』(文化2年、 1805) の中で 「信ジ難シ」 と言葉厳しく判定した。と ころが、昭和の初めごろ、青年史学者小幡氏 (後の木倉豊信氏) が、 京都の随 心院文書中に「越中守、 従五位下佐伯宿禰有若」 の署名があるのを発見、感激 にふるえる手でその古文書を手にとって確認された。 延喜5年 (905) 7月11 日の日付であった。 もしこの一通が見つからなかったら、 有若は架空人物の烙 印を押されたまま、 永久に史学界から葬り去られたことであろう。史料残存の 偶然性ということの恐ろしさをつくづく思うのである。
それにしても、立山開山伝説に有若が登場するということは、この伝説が、 有若の名がまだしっかり記憶されていた時代に成立したものであることを裏書 して貴重である。
なお『大日本史料』 第1編2に収録された『師資相承』 という史料には、天 台宗園城寺(三井寺)座主で昌泰2年 (899) 寂した康済律師について 「越前 国人、 紀氏、 越中立山建立」 と記す。 ほぼ佐伯有若と同時代の人であるが、 「立山建立」とは、具体的にどのような事実を意味するのか。 それと慈興との関係 はどうなるのか。 僧慈興が立山を開いたとき、天台座主の高僧康済の臨席を仰 いで、はなばなしく法会を挙行したのか。 種々臆測されているが、 確実なこと はいっさい不明である。
佐伯一族の護持して来た立山山麓の芦峅岩峅両寺は天台宗である。 『今昔 物語』などの伝える立山伝説中には、しばしば天台宗近江三井寺 (園城寺)の 僧が登場する。 芦峅の村はずれに切り立った岩壁をエンジョウジ壁と称してい るが、 エンジョウジと園城寺とは発音が近く、園はエンともオンとも読まれる 字である。これらの諸点は、あらためて康済律師の存在を思わせるものがある。
それにしても、立山開山伝説に有若が登場するということは、この伝説が、 有若の名がまだしっかり記憶されていた時代に成立したものであることを裏書 して貴重である。
なお『大日本史料』 第1編2に収録された『師資相承』 という史料には、天 台宗園城寺(三井寺)座主で昌泰2年 (899) 寂した康済律師について 「越前 国人、 紀氏、 越中立山建立」 と記す。 ほぼ佐伯有若と同時代の人であるが、 「立山建立」とは、具体的にどのような事実を意味するのか。 それと慈興との関係 はどうなるのか。 僧慈興が立山を開いたとき、天台座主の高僧康済の臨席を仰 いで、はなばなしく法会を挙行したのか。 種々臆測されているが、 確実なこと はいっさい不明である。
佐伯一族の護持して来た立山山麓の芦峅岩峅両寺は天台宗である。 『今昔 物語』などの伝える立山伝説中には、しばしば天台宗近江三井寺 (園城寺)の 僧が登場する。 芦峅の村はずれに切り立った岩壁をエンジョウジ壁と称してい るが、 エンジョウジと園城寺とは発音が近く、園はエンともオンとも読まれる 字である。これらの諸点は、あらためて康済律師の存在を思わせるものがある。
開山年代をめぐって
立山開山に関する最古の文献 『伊呂波字類抄』 十巻本には、山を開いた年代 については何も記していないが、 『類聚既験抄』 になると、 伝承内容はもっと も古い姿をとどめていながら、 「文武天皇御宇、 大宝元年初めて建立する所な り」と開山年を明記している。 『古事記』はほとんど年月日を記さず、 『日本書 紀』は伝承自体には古姿をとどめながら、 すべての出来事に年月日を振り当て て、後事的作為を感じさせるのが連想される。 江戸時代の 『倭漢三才図会』(正 徳3年、 1713) も、地もと芦峅・岩峅の坊々に伝わる立山開山縁起諸本も、す べて 「文武天皇大宝元年」 から説き起こし、この年を重視している。
佐伯有若の実在の確かめられるのは延喜5年 (905) であるから、 大宝元年 (701)との間に約200年の開きがある。 大宝元年を 「根拠なし」 としていち早 く否定したのは佐伯有義博士であった。 博士は岩峅出身。 つまり立山開山伝説 の佐伯有若の子孫と称する一族の出である。
しかし、劔岳・大日岳出土錫杖頭の古さから考えると、 慈興の開山に先立っ て立山山中を修行の場とした者がなかったとはいいきれぬであろう。 芦峅では 慈興上人を「開祖」 と称したが、 岩峅では慈興上人を「中興の祖」と称し、そ のため物議をかもしたことがあった。 中興という以上、 慈興開山以前の行者の 存在を積極的に肯定しているのである。 山麓各地に寺々を建て、 立山信仰の基 地を築いたから慈興は開山上人と敬われたが、それ以前の名も知れぬ山中修行者の埋もれた活躍にも思いをいたさねばならぬと思うのである
『伊呂波字類抄』 十巻本の成立は天養一治承年間 (1144?1181) といわれる。 有若実在の905年から数えて約250年後である。 歴史的事実が語り伝えられる うちに神話化してゆくには5、60年の歳月を要するといわれる。 慈興(有若) 立山開山伝説は、 有若の名が人々に記憶されている範囲で、しかも適度の期間 をかけて熟成され、やがて文献に載せられ、 さらに200年溯らせた年代を付与 されて完成したのである。
それにしても、 大宝元年をあのように強く主張するのはどうしてか。「根拠 なし」で片づけていいのか。 仏教的開山以前、 山麓に神社を設置した年か、何 か立山信仰にとって重要な意味を持つ時点として、語り継ぎ、 言い継がれて来 た記念の年ではなかったのか。 その思いを私は払拭しきれないのである。
佐伯有若の実在の確かめられるのは延喜5年 (905) であるから、 大宝元年 (701)との間に約200年の開きがある。 大宝元年を 「根拠なし」 としていち早 く否定したのは佐伯有義博士であった。 博士は岩峅出身。 つまり立山開山伝説 の佐伯有若の子孫と称する一族の出である。
しかし、劔岳・大日岳出土錫杖頭の古さから考えると、 慈興の開山に先立っ て立山山中を修行の場とした者がなかったとはいいきれぬであろう。 芦峅では 慈興上人を「開祖」 と称したが、 岩峅では慈興上人を「中興の祖」と称し、そ のため物議をかもしたことがあった。 中興という以上、 慈興開山以前の行者の 存在を積極的に肯定しているのである。 山麓各地に寺々を建て、 立山信仰の基 地を築いたから慈興は開山上人と敬われたが、それ以前の名も知れぬ山中修行者の埋もれた活躍にも思いをいたさねばならぬと思うのである
『伊呂波字類抄』 十巻本の成立は天養一治承年間 (1144?1181) といわれる。 有若実在の905年から数えて約250年後である。 歴史的事実が語り伝えられる うちに神話化してゆくには5、60年の歳月を要するといわれる。 慈興(有若) 立山開山伝説は、 有若の名が人々に記憶されている範囲で、しかも適度の期間 をかけて熟成され、やがて文献に載せられ、 さらに200年溯らせた年代を付与 されて完成したのである。
それにしても、 大宝元年をあのように強く主張するのはどうしてか。「根拠 なし」で片づけていいのか。 仏教的開山以前、 山麓に神社を設置した年か、何 か立山信仰にとって重要な意味を持つ時点として、語り継ぎ、 言い継がれて来 た記念の年ではなかったのか。 その思いを私は払拭しきれないのである。
立山曼荼羅
1.立山曼荼羅の主題 「立山開山縁起」
プロローグの一節で、 立山は、 自然のなかで地獄と浄土といった仏教世界が 一緒に体験できる、 世にも稀な人間救済空間であると述べた。 そのような立山 を、仏の阿弥陀如来のお告げによって開山 (仏教修行ができるように、 登山道 を整備したり堂舎を建てたりする) した人物が 「佐伯有頼」である。地元富山 では平成13年、立山開山 1300年を記念し、立山連峰を一望できる富山市の呉 羽山展望台にその少年像が建てられたりもして一時話題になった。 この佐伯有 頼の立山開山にまつわる物語を記したものが、 「立山開山縁起」 である。
同縁起には、『類聚既験抄』(鎌倉時代編纂) や 『伊呂波字類抄』 十巻本の「立 山大菩薩顕給本縁起」(鎌倉時代増補)、『神道集』巻四の 「越中立山権現事」(南 北朝時代編纂)、『和漢三才図会』(江戸時代正徳期の編纂) など、いくつもの 種類が見られる。 また、 このほかにも、 立山信仰の拠点集落であった立山山麓 の芦峅寺と岩峅寺に、 宿坊衆徒や社人により江戸時代中期から末期にかけて制 作された 「立山大縁起」 や 「立山小縁起」、「立山略縁起」 などが数点見られる。
そこで、これらのなかから、ここでは江戸時代中期の百科事典 『和漢三才図 会』に掲載された内容に基づき、 そのあらすじを見ていきたい。
文武天皇の大宝元年 (701)、天皇は夢の中で阿弥陀如来から、 「四条大納言 の佐伯有若を越中国司に任じれば国家は安穏である」と告げられた。 そこで、 天皇は夢から覚めると、 すぐに有若を越中国司に任じた。命を受けた有若と嫡 男の有頼は、 越中国の保伏山 (現在の魚津市布施のあたり)に移住した。
ある日、東南の方向から白鷹が飛来して有若の拳に止まった。 有若は喜んで その白鷹を育てていく。 ある日、有頼は父 (有若) に頼んで白鷹を借り、 鷹狩 りをした。 しかし、そのうち白鷹は突然どこかに飛び去ってしまう。 有頼はあ ち こちらを探すが見つからない。 その時、 森尻の権現が現れて「おまえは東 南の方向を訪ねるがよい」 と告げた。 お告げに従い山中深く入ったが、日が暮れたので岩の間に野宿した。
翌朝、岩峅の林で1人の老人に会った。 老人は「おまえが探す白鷹は今、横 江の林にいる」と告げた。 有頼があなたは誰かと問うと、「私は当山の刀尾天 神だ」と答えて去った。 有頼はお礼を述べて、さらに山中深くへと入って行っ た。 すると突然、 獰猛な熊が駈けてきて有頼に襲いかかった。 有頼はとっさに 熊に向かって矢を射ると、 矢は熊の胸に命中した。 しかし、 熊は絶命せず玉殿 窟(立山山中室堂に実在する洞穴)に入った。 追跡して洞穴に入ると、そこに は阿弥陀如来と観音菩薩、 勢至菩薩の三尊の仏像が安置されていた。それらを 拝んでよく見ると、阿弥陀如来の胸には自分が射た矢が刺さっていた。
有頼は驚くと同時に怪しんだ。 すると阿弥陀如来は有頼に、 「私は乱れた世 の人々を救うために地獄や浄土などの世界をこの山に表して、 おまえを待って いた。だからその方法として有若を越中国司にした。 白鷹は劔山刀尾天神であ る。熊は私である。 おまえは早く僧侶になり、 立山を開くがよい」と告げた。 有頼はこの霊異に深く感動し涙を流した。
のちに有頼は説法ヶ原の五智寺に住む僧侶慈朝を訪ね、 指導を受けてみずか らも僧侶となり、 慈興と名乗った。 そして、 立山大権現の大宮などの社を建て た。また立山に入山し、 小山大明神のお告げによって浄土山に登り、阿弥陀三 尊と二十五菩薩を拝んだ。
この物語のうち、 たとえば本書で基本テキストとする立山曼荼羅 『大仙坊A 本』などに具体的に描かれている図柄は、画面に向かって下段左端の布施城で ある (大仙坊A本1、 以下、冒頭モノクロ図解 『大仙坊 A 本』 を参照)。 その すぐそばに、白鷹を逃がしてしまった有頼と家来の図柄が描かれている。また 岩峅寺を過ぎたあたりの岩の上に、逃げた白鷹が描かれている (大仙坊A本2)。 さらに画面下段中央には、熊に矢を射た有頼が、手負いになった熊 (ツキノワ グマ)を追跡する場面が描かれている (大仙坊A本3)。 この曼荼羅では有頼は武士として描かれ、 陣笠に鎧を着けた姿で表現されている。
ところで、 前述の 「立山開山縁起」 の内容は、 百科事典『和漢三才図会』に 掲載されたものなので、うまく要約されている。 しかしかえってそれが災いし、脚色が少なく淡泊である。
では、これが人々を楽しませた 「絵解き」 を意識するとどうなるのか。 岩峅 寺の立山曼荼羅に対しては、 絵解き台本 『立山手引草』(岩峅寺延命院所蔵) が現存するものの、 本書で基本テキストとする岩峅寺の立山曼荼羅に対しては、 そういった資料が見当たらない。 ただし、 芦峅寺には、衆徒が絵解きした際、 必要最低限の台本として活用されていたと思われる 「立山略縁起」 があり、と りわけ宿坊家相真坊に伝わる略縁起の内容は、 芦峅寺の立山曼荼羅の図柄とみ ごとに合致する。
そこで、参考までにこの縁起から、 阿弥陀如来が現れるクライマックスの場面を見ておこう。
有頼公驚き、窟の内を窺へたまへば、 麓において熊に射たまひし箭は金色生 身の弥陀仏の胸に逆立ち、 血汐染々と流るあり。 鷹は則ち大聖世尊不動明王と 現れたまふ。天より諸仏菩薩囲繞し、 摩訶曼陀羅の花は降り散らせば、 極楽浄 土に異ならず。 これはと驚き、 吾こそは凡眼愚絵の雲厚く、 誠に鳥獣と思ひ、 仏身を穢し、 これぞ五逆重罪の大悪人と弓箭□投捨て、腰刀抜きて鬢髪を切り、 綾羅錦の衣裳を捨て、 ただ一心に低頭沸泣したまふに、この時紫雲に乗りたま ひ、諸仏菩薩は残らず還帰本土したまへる。
どうだろう、この文体には、 何となく絵解きを意識した講談的な口調が感じ られはしないだろうか。 実際にこの縁起を意識しながら芦峅寺系立山曼荼羅の 玉殿窟の場面 (大仙坊A本4) に目を転じると、 縁起の通り、 窟のなかに金色 の阿弥陀如来が生身の姿で描かれ、 その胸には矢が刺さり血が流れている。 には、不動明王も描かれている。 仏を前に佐伯有頼は合掌して平伏する。 よく見ると鎧・兜は脱がれ、頭の髷が切り落とされている。
同縁起には、『類聚既験抄』(鎌倉時代編纂) や 『伊呂波字類抄』 十巻本の「立 山大菩薩顕給本縁起」(鎌倉時代増補)、『神道集』巻四の 「越中立山権現事」(南 北朝時代編纂)、『和漢三才図会』(江戸時代正徳期の編纂) など、いくつもの 種類が見られる。 また、 このほかにも、 立山信仰の拠点集落であった立山山麓 の芦峅寺と岩峅寺に、 宿坊衆徒や社人により江戸時代中期から末期にかけて制 作された 「立山大縁起」 や 「立山小縁起」、「立山略縁起」 などが数点見られる。
そこで、これらのなかから、ここでは江戸時代中期の百科事典 『和漢三才図 会』に掲載された内容に基づき、 そのあらすじを見ていきたい。
文武天皇の大宝元年 (701)、天皇は夢の中で阿弥陀如来から、 「四条大納言 の佐伯有若を越中国司に任じれば国家は安穏である」と告げられた。 そこで、 天皇は夢から覚めると、 すぐに有若を越中国司に任じた。命を受けた有若と嫡 男の有頼は、 越中国の保伏山 (現在の魚津市布施のあたり)に移住した。
ある日、東南の方向から白鷹が飛来して有若の拳に止まった。 有若は喜んで その白鷹を育てていく。 ある日、有頼は父 (有若) に頼んで白鷹を借り、 鷹狩 りをした。 しかし、そのうち白鷹は突然どこかに飛び去ってしまう。 有頼はあ ち こちらを探すが見つからない。 その時、 森尻の権現が現れて「おまえは東 南の方向を訪ねるがよい」 と告げた。 お告げに従い山中深く入ったが、日が暮れたので岩の間に野宿した。
翌朝、岩峅の林で1人の老人に会った。 老人は「おまえが探す白鷹は今、横 江の林にいる」と告げた。 有頼があなたは誰かと問うと、「私は当山の刀尾天 神だ」と答えて去った。 有頼はお礼を述べて、さらに山中深くへと入って行っ た。 すると突然、 獰猛な熊が駈けてきて有頼に襲いかかった。 有頼はとっさに 熊に向かって矢を射ると、 矢は熊の胸に命中した。 しかし、 熊は絶命せず玉殿 窟(立山山中室堂に実在する洞穴)に入った。 追跡して洞穴に入ると、そこに は阿弥陀如来と観音菩薩、 勢至菩薩の三尊の仏像が安置されていた。それらを 拝んでよく見ると、阿弥陀如来の胸には自分が射た矢が刺さっていた。
有頼は驚くと同時に怪しんだ。 すると阿弥陀如来は有頼に、 「私は乱れた世 の人々を救うために地獄や浄土などの世界をこの山に表して、 おまえを待って いた。だからその方法として有若を越中国司にした。 白鷹は劔山刀尾天神であ る。熊は私である。 おまえは早く僧侶になり、 立山を開くがよい」と告げた。 有頼はこの霊異に深く感動し涙を流した。
のちに有頼は説法ヶ原の五智寺に住む僧侶慈朝を訪ね、 指導を受けてみずか らも僧侶となり、 慈興と名乗った。 そして、 立山大権現の大宮などの社を建て た。また立山に入山し、 小山大明神のお告げによって浄土山に登り、阿弥陀三 尊と二十五菩薩を拝んだ。
この物語のうち、 たとえば本書で基本テキストとする立山曼荼羅 『大仙坊A 本』などに具体的に描かれている図柄は、画面に向かって下段左端の布施城で ある (大仙坊A本1、 以下、冒頭モノクロ図解 『大仙坊 A 本』 を参照)。 その すぐそばに、白鷹を逃がしてしまった有頼と家来の図柄が描かれている。また 岩峅寺を過ぎたあたりの岩の上に、逃げた白鷹が描かれている (大仙坊A本2)。 さらに画面下段中央には、熊に矢を射た有頼が、手負いになった熊 (ツキノワ グマ)を追跡する場面が描かれている (大仙坊A本3)。 この曼荼羅では有頼は武士として描かれ、 陣笠に鎧を着けた姿で表現されている。
ところで、 前述の 「立山開山縁起」 の内容は、 百科事典『和漢三才図会』に 掲載されたものなので、うまく要約されている。 しかしかえってそれが災いし、脚色が少なく淡泊である。
では、これが人々を楽しませた 「絵解き」 を意識するとどうなるのか。 岩峅 寺の立山曼荼羅に対しては、 絵解き台本 『立山手引草』(岩峅寺延命院所蔵) が現存するものの、 本書で基本テキストとする岩峅寺の立山曼荼羅に対しては、 そういった資料が見当たらない。 ただし、 芦峅寺には、衆徒が絵解きした際、 必要最低限の台本として活用されていたと思われる 「立山略縁起」 があり、と りわけ宿坊家相真坊に伝わる略縁起の内容は、 芦峅寺の立山曼荼羅の図柄とみ ごとに合致する。
そこで、参考までにこの縁起から、 阿弥陀如来が現れるクライマックスの場面を見ておこう。
有頼公驚き、窟の内を窺へたまへば、 麓において熊に射たまひし箭は金色生 身の弥陀仏の胸に逆立ち、 血汐染々と流るあり。 鷹は則ち大聖世尊不動明王と 現れたまふ。天より諸仏菩薩囲繞し、 摩訶曼陀羅の花は降り散らせば、 極楽浄 土に異ならず。 これはと驚き、 吾こそは凡眼愚絵の雲厚く、 誠に鳥獣と思ひ、 仏身を穢し、 これぞ五逆重罪の大悪人と弓箭□投捨て、腰刀抜きて鬢髪を切り、 綾羅錦の衣裳を捨て、 ただ一心に低頭沸泣したまふに、この時紫雲に乗りたま ひ、諸仏菩薩は残らず還帰本土したまへる。
どうだろう、この文体には、 何となく絵解きを意識した講談的な口調が感じ られはしないだろうか。 実際にこの縁起を意識しながら芦峅寺系立山曼荼羅の 玉殿窟の場面 (大仙坊A本4) に目を転じると、 縁起の通り、 窟のなかに金色 の阿弥陀如来が生身の姿で描かれ、 その胸には矢が刺さり血が流れている。 には、不動明王も描かれている。 仏を前に佐伯有頼は合掌して平伏する。 よく見ると鎧・兜は脱がれ、頭の髷が切り落とされている。
2.物語性豊かな芦峅寺相真坊の「立山略縁起」
前節で、芦峅寺衆徒が立山曼荼羅を絵解きした際、手頃な長さで、どことな く講談調の 「立山略縁起」 が台本になり得たのではないかと述べたが、 次の相真坊の略縁起 (筆者が内容を整理したもの)は、 それを実によく示している。
この縁起は短いながらも、 物語性が豊かである。
佐伯有若、 越中に赴任する
近江国志賀の都で暮らしていた佐伯有若は、大宝元年(701) 2月、 文武天 皇の命を受け、 越中守として越中国に赴任し、 新川郡字布施の院に居城を構えた。子宝に恵まれない有若夫妻
越中国での有若は人徳をもって国を治めた。 しかし、 40歳になっても家督 を相続する子どもができなかった。 そこで、 有若とその妻は、城内に祀る屋敷 神に、子宝が授かるようにとお祈りした。神様の顕現
夫妻は37日の日数をあらかじめ定めて、毎日、神様にお祈りを捧げていたが、 その最終日、 眠っていると不思議なことに宮殿の扉が開き、 髪を垂れた 80歳 ぐらいの老人が、 右手に金鈴を持ち、左手に白羽の鷹を止まらせて現れた。老 人は 「三世大千世界を訪ねても、おまえが授かる子どもはいないだろう。 だが、 おまえの願望は見捨て難い。 だから男の子を1人授けてあげよう。 ただし、そ の子が生まれたならば、 この白鷹も一緒に育て、 信心しなさい」と告げて、消えて行った。有若夫妻に男子誕生
夫婦が夢から覚めると、 妻は臨月になっていて、じきに男の子が生まれた。 この子に対する夫婦の寵愛は深く、 有頼と名づけた。
有頼の成長
やがてあっという間に時が過ぎ、 有頼は16歳になった。 しかし、 神様の予言した白羽の鷹はいまだに手に入らない。 日本 60余州で鷹狩りをしても、白羽の鷹に出会うことはなく、 残念に思いながら過ごしていた。有若、白鷹を手に入れる
翌年(大宝2年) 6月、 有若が炎暑を避けるため院に入って休息していると、 天に白羽の鷹が飛んでいるのを見つけた。 金の扇を上げて呼び寄せると、白鷹 は舞い降りてきて有若の右手に止まった。 有若は白鷹を捕まえると、 すぐに鷹 部屋という名前の宮殿閣を造立し、 そこで白鷹を大事に育てた。有頼、 鷹狩りに出る
9月13日、国中で検田を行った際、 有頼は父が寵愛する白鷹をかかえ、 天 神山の下尾崎野に出て、ひそかに鷹狩りをした。 しかし9月19日の日中、 白 鷹は南天に逃げて行き、 遥か向こうの山に姿を隠した。激怒する有若
この事件が家来から城内に伝えられると、 それを聞いた父有若は激怒した。 そして言うには、「私の寵愛する白鷹を持ち帰らなければ顔を合わすことは許 さない」と。このことを、 有頼に早急に家来をよこして伝えた。有頼、家来と別れる
有頼にお伴した家来たちはこの話を聞き、誰一人言葉を発する者もなく、み な押し黙った。 やがて忠臣の卜部吉胤が静かに口を開いた。 「大殿様 (有若) が、 たかだか白鷹1羽のために殿様 (有頼)を勘当なされるとは、 何かわけがある に違いありません。 万一、 殿様に災いが起きてはいけませんから、自分たちは どこまでも殿様について行き、 一緒に白鷹を探したいのですが、 だからといっ て、 大殿様のご命令にも背けません。 ですから、 殿様より一足先に城に戻って、 事の成り行きをうかがうことにさせてください」。
有頼と家来たちは相談の末、 卜部の意見に従うことにした。 家来たちは皆、悲嘆の涙に袖をしぼって帰って行った。1人で白鷹を探す有頼
あとに有頼が1人残された。 天より堕とされた心地がして胸が痛み、手をこ まぬきながら思案した。 しかし、気を取り直し、 父有若のことは吉胤に任せて おけば心配ないと思い、 自分は早く白鷹を探し出そうと、 東方の山を目当てに して山中へ分け入った。 しかし、 有頼は官人なので、 慣れない山歩きは困難を きわめた。足が疲れて歩くこともつらくなってきた。すでに太陽も山に隠れ、 代わって月が東の山の頂に現れた。 しばらくあたりを見ていると、 崖の上に古 木が生えており、その陰に洞穴 (獅子ヶ鼻か) があったので、そこで野宿した。有頼、白鷹を見つける
夜が明け、 再び原野 (弥陀ヶ原か) に出て、 あてもなく白鷹を探していると、 遥か向こうの山頂に古い松の木があり、 そこに白鷹が翼を垂れて止まっている のを見つけた。「ああ嬉しい、 やっと父の怒りもおさまるだろう」と思い、鈴 を鳴らして白鷹を呼び寄せた。すると鷹は舞い降り、有頼のもとに戻ってきた。有頼、熊に襲われ白鷹が逃げる
しかし、まさにその時、 突然獰猛な大熊が現れ吠えたので、 白鷹は驚いて再 び飛び去った。さらに有頼に襲いかかってきたので、有頼はとっさに熊に向かっ て矢を射ると、矢は熊の胸 月の輪) に命中した。 しかし、 熊は絶命せず、矢 が刺さったままで血を流しながら東南のほうへ逃げて行った。 白鷹もその熊と ともに飛んで行く。 有頼は怒りながら熊と白鷹を追跡した。 そうこうするうち、 その日も暮れ、木の根っこの所で岩の角を枕にして野宿した。神様の顕現とお告げ
その夜、 有頼の夢の中に不思議なるかな、 80歳ぐらいの老人が現れ、 「おま えの探す熊と白鷹は、ここより東南の高峰に登って行った。 熊の血の跡を追って行くがよい」と告げ、 消え去った。夢が覚めると、有頼は喜んで立山の高峰 を登って行った。阿弥陀如来と不動明王の顕現
山中に洞窟があり、 その中へ熊と白鷹は入って行った。 有頼はようやく白鷹 を取り戻すことができると思い、喜んで洞窟に向かって行った。 その時、不思 議なるかな、 洞窟の内外が光り輝いた。 有頼が驚いて窟の中をうかがうと、そ こに金色で生身の阿弥陀如来が現れた。 そして阿弥陀の胸には有頼が山麓で熊 に射た矢が刺さり、 血が流れている。 阿弥陀とともに不動明王も現れたが、そ れは白鷹だった。 さらに、 天空より諸仏諸菩薩が来迎し、 花が降ってきて、 その光景は極楽浄土の世界に他ならなかった。有頼、出家する
有頼は鳥獣と思い仏を傷つけた罪に恐れおののき、 弓矢を投げ捨て、 腰刀 で鬢髪を切り、 狩装束も脱いでひたすら頭を垂れていた。 そのうち、 紫色の雲 に乗って、 諸仏や諸菩薩は残らず極楽浄土の世界に帰って行った。薬勢仙人の顕現
あとに残された有頼は、次第に身体の疲れを感じ動けなくなった。 仏を危め た自分の罪を懺悔し自害しようと決心したとき、 薬勢仙人が現れ神丹(薬)を くれた。これを飲めば元気になり、 悩みも忘れるという。慈朝仙人の顕現
さらに薬勢仙人が呪文を唱えると年老いた僧侶が現れて、 「私は天竺五台山 文殊菩薩の弟子の慈朝仙人である。 おまえは知らないだろうが、 立山は日本一 の霊山である。 山麓より峰まで9里8丁あって、 峰には9品の浄土があり 谷 には 136 地獄がある。 すべての人々にとって勧善懲悪の山である。 おまえが立 山を開山するならば、 その功徳は果てしなく大きい」 と告げた。有頼、立山を開山する
有頼はつぎつぎ起こる霊異に感動し、一念発起してすぐに慈朝の弟子となり、
修行して菩薩戒を授けられた。 僧侶となった有頼は慈興と改名し、1000日の間、 山中の洞窟に籠もり、 厳しい修行をして立山を開いた。 文武天皇の勅願所となる
さらに、近江国志賀の都に上り、宮中で自分が体験した立山開山にまつわる 不思議な事跡を伝えた。それによって、 都より北の涅槃門に当たる立山は、文 武天皇の勅願所に指定された。 7カ所に7000 坊 49 カ院寺を造立し、麓の芦峅 の里に七堂伽藍を建立した。そしてここに弥陀・釈迦・大日の三尊を祀った。有頼、亡くなる
その後、 和銅7年 (714) 寅の6月13日、 慈興は83歳で亡くなった。 3.立山開山について
明治時代、立山連峰の大日岳と劔岳から、 奈良時代末期から平安時代初期の 制作と推定される銅錫杖頭が相次いで発見された。 それらにより、平安初期に は、立山もすでに諸国の山岳霊場を巡る山間修行者たちの修行場になっていた ことがうかがわれる。 このほか、 平安時代の仏教説話集 『大日本国法華経験記』 や『今昔物語集』所収の立山地獄説話に、諸国回峰の修行者が立山地獄に堕ち た亡霊と遭遇する話が見られるが、 それなども立山が開山される以前に、諸国 の山岳霊場の1カ所として立山を訪れる修行者たちが存在したことを示すもの であろう。こうした山間修行者は不動信仰の伝播者でもあった。
不動明王は五大明王のうちの中心的な明王であり、 平安貴族社会では真言寺 院や天台寺院に同尊を祀り、疫病退散や国家・社会の平安を祈願して加持祈? が行われてきた。 そして当時の不動信仰は、たとえば 『平安物語』 に、 真言僧 文覚が紀伊国熊野の那智大滝で21日の荒行を行い、 不動明王の加護によって助けられたといった記載があることや、 『天台南山無動寺建立和尚伝』に比叡 山の千日回峰行の開創者と伝える無動寺の相応和尚 (831~918) が、 葛川の 霊瀑で不動明王を感得したといった記載に表れているように、回峰行や修験道 と深く結びついていた。
このような不動信仰をもった山間修行者の痕跡は、 立山山麓上市町(現、富 山県上市町)に所在する大岩山日石寺の不動明王磨崖仏にも見られる。同尊は 脇侍の矜羯羅童子・制?迦童子とともに平安時代初期の成立と推測されている。 なお、同岩に刻まれている阿弥陀如来坐像と僧形像は、 越中に阿弥陀信仰が伝 播した平安時代後期の追刻と推測されている。
一方、こうした山間修行者のなかには、 立山山麓に定住して宗教活動を実践 する者が出はじめ、 次第に組織や堂舎を整えていった。 立山山麓の芦峅寺閻魔 堂には、平安時代の成立と推測される木造不動明王頭部が1体残っている。 同 尊頭部は一木造りで全長は60センチもあるが、 差し頸形式になっているので、 もとはそれに見合う巨大な胴体部も存在したはずである。 この尊像の存在によ り、遅くとも平安時代末期頃までには、 芦峅寺か、あるいはその界隈に不動信 仰が伝播していたことや、 こうした尊像の安置および維持管理を可能とする宗 教施設・組織が存在していたことが推測される。
鎌倉時代に増補された 『伊呂波字類抄』 十巻本所収「立山大菩薩」 の条には、 立山開山者の慈興が、 立山山麓で先行的に宗教活動を行っていた薬勢の弟子と なり、 その後、 師弟協力して山麓に 「芦峅寺根本中宮」 を含む立山信仰の拠点 寺院を建立したという記載が見られる。すなわち、 常願寺川の南の本宮・光明山・ 報恩寺 (現、富山県大山町)は薬勢が、 常願寺川の北の芦峅寺根本中宮・安楽 寺・高禅寺・禅光寺 (現、富山県立山町)などは慈興が開いたというものであ るが、この頃には、 立山はもうとっくの昔に開山されてしまっているとみてよ い。とくに芦峅寺について言えば、 芦峅寺雄山神社の開山堂には鎌倉時代初期 の作品と推測される木造立山開山慈興上人坐像が安置されているが、 それが成 立した時期までには、 前述の通り芦峅寺の本尊を祀る中核的な堂舎は当然のこ と、他の堂塔伽藍もある程度整えられ、 芦峅寺は宗教村落として、 組織的にも施設的にも確立していたことがうかがわれる。
では、現実に立山はいつ頃開山されたのか。 『師資相承』 という史料には、 天台座主 (天台宗比叡山延暦寺の管主)であった学僧康済の功績として、 「越 中立山建立」と記されている。 座主まで務めた人物の生涯最大の功績としてそ れだけを記すのだから、 それはよほど意味のあることだったに違いない。 しか し残念ながらこの史料からは、立山建立の具体的な内容が全くつかめない。 康 済は昌泰2年(899)に72歳で亡くなっているので、彼の活躍時期から考える と、9世紀後半には、 立山のどこかに天台宗寺門派の教団勢力の拠点地ができ ていたと思われる。 そしてそのことは、 前述の芦峅寺の木造不動明王頭部の一 件から少し時間をおいてのこととしてとらえるとうまく符合し、 こうした中央 の教団勢力の立山への進出や現地における拠点地の成立を“立山開山” の1つ の意味としてみることも可能であろう。
不動明王は五大明王のうちの中心的な明王であり、 平安貴族社会では真言寺 院や天台寺院に同尊を祀り、疫病退散や国家・社会の平安を祈願して加持祈? が行われてきた。 そして当時の不動信仰は、たとえば 『平安物語』 に、 真言僧 文覚が紀伊国熊野の那智大滝で21日の荒行を行い、 不動明王の加護によって助けられたといった記載があることや、 『天台南山無動寺建立和尚伝』に比叡 山の千日回峰行の開創者と伝える無動寺の相応和尚 (831~918) が、 葛川の 霊瀑で不動明王を感得したといった記載に表れているように、回峰行や修験道 と深く結びついていた。
このような不動信仰をもった山間修行者の痕跡は、 立山山麓上市町(現、富 山県上市町)に所在する大岩山日石寺の不動明王磨崖仏にも見られる。同尊は 脇侍の矜羯羅童子・制?迦童子とともに平安時代初期の成立と推測されている。 なお、同岩に刻まれている阿弥陀如来坐像と僧形像は、 越中に阿弥陀信仰が伝 播した平安時代後期の追刻と推測されている。
一方、こうした山間修行者のなかには、 立山山麓に定住して宗教活動を実践 する者が出はじめ、 次第に組織や堂舎を整えていった。 立山山麓の芦峅寺閻魔 堂には、平安時代の成立と推測される木造不動明王頭部が1体残っている。 同 尊頭部は一木造りで全長は60センチもあるが、 差し頸形式になっているので、 もとはそれに見合う巨大な胴体部も存在したはずである。 この尊像の存在によ り、遅くとも平安時代末期頃までには、 芦峅寺か、あるいはその界隈に不動信 仰が伝播していたことや、 こうした尊像の安置および維持管理を可能とする宗 教施設・組織が存在していたことが推測される。
鎌倉時代に増補された 『伊呂波字類抄』 十巻本所収「立山大菩薩」 の条には、 立山開山者の慈興が、 立山山麓で先行的に宗教活動を行っていた薬勢の弟子と なり、 その後、 師弟協力して山麓に 「芦峅寺根本中宮」 を含む立山信仰の拠点 寺院を建立したという記載が見られる。すなわち、 常願寺川の南の本宮・光明山・ 報恩寺 (現、富山県大山町)は薬勢が、 常願寺川の北の芦峅寺根本中宮・安楽 寺・高禅寺・禅光寺 (現、富山県立山町)などは慈興が開いたというものであ るが、この頃には、 立山はもうとっくの昔に開山されてしまっているとみてよ い。とくに芦峅寺について言えば、 芦峅寺雄山神社の開山堂には鎌倉時代初期 の作品と推測される木造立山開山慈興上人坐像が安置されているが、 それが成 立した時期までには、 前述の通り芦峅寺の本尊を祀る中核的な堂舎は当然のこ と、他の堂塔伽藍もある程度整えられ、 芦峅寺は宗教村落として、 組織的にも施設的にも確立していたことがうかがわれる。
では、現実に立山はいつ頃開山されたのか。 『師資相承』 という史料には、 天台座主 (天台宗比叡山延暦寺の管主)であった学僧康済の功績として、 「越 中立山建立」と記されている。 座主まで務めた人物の生涯最大の功績としてそ れだけを記すのだから、 それはよほど意味のあることだったに違いない。 しか し残念ながらこの史料からは、立山建立の具体的な内容が全くつかめない。 康 済は昌泰2年(899)に72歳で亡くなっているので、彼の活躍時期から考える と、9世紀後半には、 立山のどこかに天台宗寺門派の教団勢力の拠点地ができ ていたと思われる。 そしてそのことは、 前述の芦峅寺の木造不動明王頭部の一 件から少し時間をおいてのこととしてとらえるとうまく符合し、 こうした中央 の教団勢力の立山への進出や現地における拠点地の成立を“立山開山” の1つ の意味としてみることも可能であろう。
4.無名の狩人から佐伯有頼の立山開山へ
日本各地の霊山の開山伝説をみていくと、 狩人が登場する場合が多い。霊山 で狩人が山の神や仏と遭遇し、その山を仏教の山として開く、あるいは、あと から入ってきた高僧に開山を譲り、その高僧が最終的な開山者になるといった 内容である。高野山や伯耆大山、英彦山、日光山などがそうした山である。参 考として、伯耆 (鳥取県) 大山の事例をみておきたい。
出雲国玉造(島根県八束郡玉湯町玉造) の狩人依道が、 美保の浦を通りかかっ たとき、海底から金色の狼が現れた。狼は依道を誘うように逃げ、大山山中の 洞に逃げ込んだ。依道が狼を射止めようと弓を構えると、矢先に地蔵菩薩が現 れた。驚き恐れる依道の前で狼が老尼に変わり、「私は登欖尼という山の神だ が、おまえに一緒に地蔵菩薩を祀ってもらうために、狼に姿を変えてここまで 導いたのだ」と告げた。これを聞いた依道は発心して出家し、 金蓮と名乗った (大山寺洞明院所蔵『大山寺縁起』より)。どうだろう、前節で紹介した「立山 「開山縁起」に何とよく似ていることか。
ところで、 鎌倉時代の 『類聚既験抄』所収の 「立山開山縁起」には、「立山 に狩人がいて熊を射殺したが、 その熊は金色の阿弥陀如来であった。 よってこ の山を立山権現という」 と、いたって簡潔に記されている。 このように、『類 聚既験抄』 の縁起では立山の開山者を前述の大山の場合と同様に狩人とするが、 おそらく、 他の霊山の事例と比較して考えても、この縁起は一連の 「立山開山 縁起」のなかで原型的なものと言えよう。
したがってこの縁起には、江戸時代に成立した一連の開山縁起よりも、かえっ て「立山開山縁起」が本来的にもつ意味が明確に表れている。 すなわち、熊は 日本のみならず世界各地で霊威をもった神聖な動物とみなされているが、この 縁起においても、 熊は立山の山の神か、あるいはその使いを象徴している。 方、 阿弥陀如来は外来宗教である仏教の仏である。 この縁起では、もともと立 山を支配していた山の神に対する信仰と、 立山にあとから入ってきた仏教の阿 弥陀如来に対する信仰とが習合し、 阿弥陀如来を本地、 立山権現を垂迹とする、 いわゆる本地垂迹思想に基づいて、 立山が仏教的な世界に展開したことが示唆 されているのである。
それでは、 佐伯有若や有頼が登場する、いわゆる脚色された内容の開山伝説 はどのようにしてできたのだろうか。鎌倉時代に増補された『伊呂波字類抄』 十巻本の「立山開山縁起」にはじめて、「越中守佐伯有若宿禰」が開山者とし て登場する。 この 「佐伯有若」 については、昭和初年、富山の歴史学者木倉豊 信氏が京都・随心院文書のなかの 「佐伯院付属状」(延喜5年〔905])に、「越 中守従五位下佐伯宿禰有若」の署名を発見し、その 10世紀初頭の実在を証明 した。
ただし、この有若その人が実際に立山を開山したかどうかは、この史料から は断定できない。むしろ、前述の『類聚既験抄』のような簡潔な縁起が「立山 開山縁起」の原型で、 それが次第に脚色されていく過程で、実在の佐伯有若が 縁起に取り込まれたと考えたほうが素直であろう。 その後、 江戸時代に成立し た多くの「立山開山縁起」では、物語に佐伯有若と有頼の親子関係が組み込ま れ、立山の開山者も有頼に移行する。
仏教民俗学者の五来重氏によると、「有頼」の「アリ」や「ヨリ」 の語は神 霊の憑依にかかわる語であり、 狩人が山の神と交信するところから、 開山者と しての有頼の名前が生まれたものと推測されている。 これはなかなか意味深い 指摘である。なぜなら、 「立山開山縁起」では、主人公の佐伯 「有頼」が阿弥 陀如来の宣託を受け、立山の開山を成就したことが物語の主要部になっている が、そこに物語を進めていくうえで、 主人公の「鷹狩り」 や、 ある意味で「熊 狩り」とも言える物語の副次的な部分は、 物語の主要部で、 本地垂迹思想に基 づき、立山の古来の支配神と外来の仏教の阿弥陀如来との習合を導き出すため に、きわめて重要な役割を果たしているからである。
このように、江戸時代の「立山開山縁起」で主人公に付加された狩猟のイメー ジは (吉祥坊本1、 以下、冒頭モノクロ図解 『吉祥坊本』を参照)、 それが物 語のなかで貴族の遊戯の狩猟に転化されていても、本質的には芦峅寺など、立 山山麓の山民たちの狩猟や焼畑を中心とした生業を強く反映していると言え る。 すなわち、 立山山麓に土着の山民たちが、 外から入ってきた宗教者や彼ら がもたらす仏教を受け入れた際、 その影響を強く受け、 彼らとともに新しい宗 教組織や信仰を築きながらも、一方では自分たちが古来守り伝えてきた山の神 に対する信仰を忘却しないように、 「立山開山縁起」に狩猟の物語を挿入する ことで残そうとしたのである。
さらに、このように考えると、 「立山開山縁起」 は、 本来的には稲作を生業 とした岩峅寺の宗教者たちの所産というよりは、むしろ狩猟や焼畑を生業とし た芦峅寺の宗教者たちの所産と言えるのではなかろうか。
出雲国玉造(島根県八束郡玉湯町玉造) の狩人依道が、 美保の浦を通りかかっ たとき、海底から金色の狼が現れた。狼は依道を誘うように逃げ、大山山中の 洞に逃げ込んだ。依道が狼を射止めようと弓を構えると、矢先に地蔵菩薩が現 れた。驚き恐れる依道の前で狼が老尼に変わり、「私は登欖尼という山の神だ が、おまえに一緒に地蔵菩薩を祀ってもらうために、狼に姿を変えてここまで 導いたのだ」と告げた。これを聞いた依道は発心して出家し、 金蓮と名乗った (大山寺洞明院所蔵『大山寺縁起』より)。どうだろう、前節で紹介した「立山 「開山縁起」に何とよく似ていることか。
ところで、 鎌倉時代の 『類聚既験抄』所収の 「立山開山縁起」には、「立山 に狩人がいて熊を射殺したが、 その熊は金色の阿弥陀如来であった。 よってこ の山を立山権現という」 と、いたって簡潔に記されている。 このように、『類 聚既験抄』 の縁起では立山の開山者を前述の大山の場合と同様に狩人とするが、 おそらく、 他の霊山の事例と比較して考えても、この縁起は一連の 「立山開山 縁起」のなかで原型的なものと言えよう。
したがってこの縁起には、江戸時代に成立した一連の開山縁起よりも、かえっ て「立山開山縁起」が本来的にもつ意味が明確に表れている。 すなわち、熊は 日本のみならず世界各地で霊威をもった神聖な動物とみなされているが、この 縁起においても、 熊は立山の山の神か、あるいはその使いを象徴している。 方、 阿弥陀如来は外来宗教である仏教の仏である。 この縁起では、もともと立 山を支配していた山の神に対する信仰と、 立山にあとから入ってきた仏教の阿 弥陀如来に対する信仰とが習合し、 阿弥陀如来を本地、 立山権現を垂迹とする、 いわゆる本地垂迹思想に基づいて、 立山が仏教的な世界に展開したことが示唆 されているのである。
それでは、 佐伯有若や有頼が登場する、いわゆる脚色された内容の開山伝説 はどのようにしてできたのだろうか。鎌倉時代に増補された『伊呂波字類抄』 十巻本の「立山開山縁起」にはじめて、「越中守佐伯有若宿禰」が開山者とし て登場する。 この 「佐伯有若」 については、昭和初年、富山の歴史学者木倉豊 信氏が京都・随心院文書のなかの 「佐伯院付属状」(延喜5年〔905])に、「越 中守従五位下佐伯宿禰有若」の署名を発見し、その 10世紀初頭の実在を証明 した。
ただし、この有若その人が実際に立山を開山したかどうかは、この史料から は断定できない。むしろ、前述の『類聚既験抄』のような簡潔な縁起が「立山 開山縁起」の原型で、 それが次第に脚色されていく過程で、実在の佐伯有若が 縁起に取り込まれたと考えたほうが素直であろう。 その後、 江戸時代に成立し た多くの「立山開山縁起」では、物語に佐伯有若と有頼の親子関係が組み込ま れ、立山の開山者も有頼に移行する。
仏教民俗学者の五来重氏によると、「有頼」の「アリ」や「ヨリ」 の語は神 霊の憑依にかかわる語であり、 狩人が山の神と交信するところから、 開山者と しての有頼の名前が生まれたものと推測されている。 これはなかなか意味深い 指摘である。なぜなら、 「立山開山縁起」では、主人公の佐伯 「有頼」が阿弥 陀如来の宣託を受け、立山の開山を成就したことが物語の主要部になっている が、そこに物語を進めていくうえで、 主人公の「鷹狩り」 や、 ある意味で「熊 狩り」とも言える物語の副次的な部分は、 物語の主要部で、 本地垂迹思想に基 づき、立山の古来の支配神と外来の仏教の阿弥陀如来との習合を導き出すため に、きわめて重要な役割を果たしているからである。
このように、江戸時代の「立山開山縁起」で主人公に付加された狩猟のイメー ジは (吉祥坊本1、 以下、冒頭モノクロ図解 『吉祥坊本』を参照)、 それが物 語のなかで貴族の遊戯の狩猟に転化されていても、本質的には芦峅寺など、立 山山麓の山民たちの狩猟や焼畑を中心とした生業を強く反映していると言え る。 すなわち、 立山山麓に土着の山民たちが、 外から入ってきた宗教者や彼ら がもたらす仏教を受け入れた際、 その影響を強く受け、 彼らとともに新しい宗 教組織や信仰を築きながらも、一方では自分たちが古来守り伝えてきた山の神 に対する信仰を忘却しないように、 「立山開山縁起」に狩猟の物語を挿入する ことで残そうとしたのである。
さらに、このように考えると、 「立山開山縁起」 は、 本来的には稲作を生業 とした岩峅寺の宗教者たちの所産というよりは、むしろ狩猟や焼畑を生業とし た芦峅寺の宗教者たちの所産と言えるのではなかろうか。
5.現在も息づく立山信仰の精神性
平成13年4月、 立山開山 1300年を記念し、健全な青少年の理想像として、 立山を開山した佐伯有頼の少年像が富山市の呉羽山展望台に建立された。この 事業に尽力されたのは立山信仰史の研究で知られる廣瀬誠氏だが、 廣瀬氏は、 富山市水橋出身の童話作家・大井令光が生前果たせなかった夢を実現させたのである。
令光の夢とは、少年少女の健全な育成を願い、度重なる苦難を乗り越えて立 山開山の大事業を達成した16歳の佐伯有頼少年を理想として、その銅像を建 立することであった。 令光は大正4年(1915)頃、有賴像の建立を発案した が、彫刻家・畑正吉に依頼し原型像を造り上げたものの、令光自身が大正 10 年(1921)に急逝したため、 果たせなかった。
ところで、いくつもある立山開山縁起のうち、江戸時代に成立した縁起のほ とんどは、開山者を佐伯有若の嫡男有頼とする。 さらに、これらのうち有頼の 年齢を 16歳とする縁起は、前節で紹介した芦峅寺相真坊所蔵の「立山略縁起」 (享保元年〔1716〕 改記) と、 岩峅寺中道坊所蔵の「立山略由来記」 (安政2年 〔1855〕) である。 とくに相真坊の縁起は、ほかの縁起に比べ開山を達成するま での有頼少年の苦難がことさら強調され、 成人儀礼 (子どもから大人になるた めの儀式)的な意味合いが多分に込められている。 具体的にそのポイントを指 摘すると次の通りである。
長く子宝に恵まれなかった佐伯有若が阿弥陀如来の霊験で子ども(有頼)を 授かる。それゆえ有若は息子有頼を溺愛するが、 有頼が16歳のとき、 鷹狩り で失敗すると、一転して獅子が自分の子をあえて谷底に突き落として厳しく鍛 えるように、 有頼を冷たく突き放してしまう。 有若は有頼に随行した家来も城 に帰るように命じ、有頼1人だけで逃げた白鷹を探索させる。 その後、有頼は 度重なる苦難を克服し立山開山を成し遂げる。
このように 16歳で立山を開山した有頼にあやかってか、 富山県内では第2 次世界大戦前までは、 「越中の男子は16歳で立山に登らなければ若連中(青年 団)に入れない」といった、 成人儀礼としての立山登山の風習が根強く残って いた。戦後は自治体主催の成人記念登山や学校活動のなかでの登山に切り替 わったが、それも危険を考慮され、次第に下火となった。
しかし近年、富山県では、県教育委員会主催 「12歳の立山夢登山」や立山 町教育委員会主催 「立山新発見! わくわくどきどきニュー立山」、県護国神 社の 「元服立山登拝」 など、 青少年の健全な育成や自然との共生を考えることを目的とした立山登山がさまざまな形で実施され、再び脚光を浴びてきている。 時代は移っても、立山開山縁起にみられる立山信仰の精神性は、その時代に合っ た形で、これからもずっと富山県民の間で引き継がれていくようである。
令光の夢とは、少年少女の健全な育成を願い、度重なる苦難を乗り越えて立 山開山の大事業を達成した16歳の佐伯有頼少年を理想として、その銅像を建 立することであった。 令光は大正4年(1915)頃、有賴像の建立を発案した が、彫刻家・畑正吉に依頼し原型像を造り上げたものの、令光自身が大正 10 年(1921)に急逝したため、 果たせなかった。
ところで、いくつもある立山開山縁起のうち、江戸時代に成立した縁起のほ とんどは、開山者を佐伯有若の嫡男有頼とする。 さらに、これらのうち有頼の 年齢を 16歳とする縁起は、前節で紹介した芦峅寺相真坊所蔵の「立山略縁起」 (享保元年〔1716〕 改記) と、 岩峅寺中道坊所蔵の「立山略由来記」 (安政2年 〔1855〕) である。 とくに相真坊の縁起は、ほかの縁起に比べ開山を達成するま での有頼少年の苦難がことさら強調され、 成人儀礼 (子どもから大人になるた めの儀式)的な意味合いが多分に込められている。 具体的にそのポイントを指 摘すると次の通りである。
長く子宝に恵まれなかった佐伯有若が阿弥陀如来の霊験で子ども(有頼)を 授かる。それゆえ有若は息子有頼を溺愛するが、 有頼が16歳のとき、 鷹狩り で失敗すると、一転して獅子が自分の子をあえて谷底に突き落として厳しく鍛 えるように、 有頼を冷たく突き放してしまう。 有若は有頼に随行した家来も城 に帰るように命じ、有頼1人だけで逃げた白鷹を探索させる。 その後、有頼は 度重なる苦難を克服し立山開山を成し遂げる。
このように 16歳で立山を開山した有頼にあやかってか、 富山県内では第2 次世界大戦前までは、 「越中の男子は16歳で立山に登らなければ若連中(青年 団)に入れない」といった、 成人儀礼としての立山登山の風習が根強く残って いた。戦後は自治体主催の成人記念登山や学校活動のなかでの登山に切り替 わったが、それも危険を考慮され、次第に下火となった。
しかし近年、富山県では、県教育委員会主催 「12歳の立山夢登山」や立山 町教育委員会主催 「立山新発見! わくわくどきどきニュー立山」、県護国神 社の 「元服立山登拝」 など、 青少年の健全な育成や自然との共生を考えることを目的とした立山登山がさまざまな形で実施され、再び脚光を浴びてきている。 時代は移っても、立山開山縁起にみられる立山信仰の精神性は、その時代に合っ た形で、これからもずっと富山県民の間で引き継がれていくようである。